このシリーズのアシスタント、サッカー大好き。夏久愛(なつくあい)です。
昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。
廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。
前回は、排出事業者の排出事業所での保管基準でしたね。今回はどんな話?
昨年度入社の2年目で、総務部環境管理課で、グループ企業を含めての廃棄物管理を担当しています。
廃棄物処理法は難しくて、どんなことに注意していけばよいのか、まだまだ判らないことも多いので、「排出事業者がやっちゃいそうなミス」なんかを中心に教わっていきたいと思います。
前回は、排出事業者の排出事業所での保管基準でしたね。今回はどんな話?
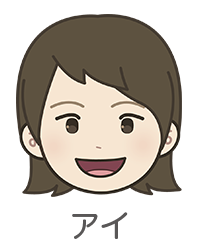

前回は保管基準のハード面。「囲い」と「掲示板」の話だったけど、今回はソフト面。じゃ、さっそく条文を見てみようか。
省令(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
省令(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
二 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
出てきましたね。第1回で登場した「共通基準」。「飛散、流出、悪臭、地下浸透、鼠や害虫の害を出してはいけない」ですね。
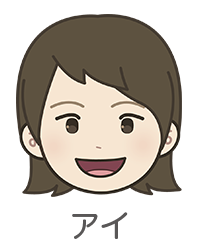

そう。これが出ないようにどうしたらいいのかを規定している。まずは第2号「イ」。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
いくら「囲い」をしっかり作っても、床が土間だと汚水が浸みていく。底面もしっかり作りなさいってことですね。ちなみに、「汚水が生ずるおそれがある場合」ってしていますけど、「汚水が生じない」ケース。つまり、土間でもいいよってケースはどのようなものなんですか?
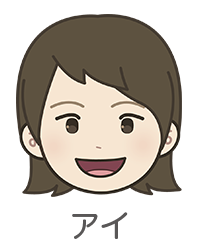

保管する産業廃棄物自体が、そもそも「汚水が生ずるおそれ」が無い場合が考えられるね。たとえば、コンクリート殻だけを保管する、とか。混在物が無いことが前提条件だけど、コンクリート殻はたとえば、元々ビルだったものでしょ。ビルは長い間雨ざらしでも汚水は出ないでしょ。
そうかぁ。そう考えれば道路のアスファルトなんかも同じですね。アスファルト道路の周辺が汚水で汚染されているなんてないですものね。
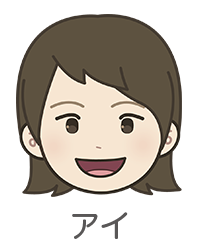

そのように考えていくと、いわゆる「安定5品目」の産業廃棄物だけなら普通は「汚水が生ずるおそれ」は無いと判断されるでしょうね。
「安定5品目」って、ガラス陶磁器くず、がれき類、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くずでしたね。安定型最終処分場に埋め立ててよいとしている産業廃棄物ですね。
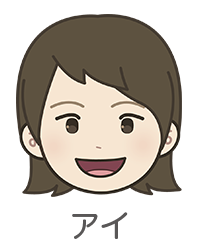

そうだね。ただ、何回か後で「埋立基準」の時に詳しく取り上げるけど、いわゆる「安定5品目」でも安定型最終処分場には埋めていけない種類がありましたね。
おっと、結構ハイレベルな問題ですね。たしか、金属くずには該当するけど鉛は溶解度が基準を上回るから入れてダメとか、容器包装廃棄物は容器に付着物が着いているから埋めちゃダメ、とかいうルールでしたね。
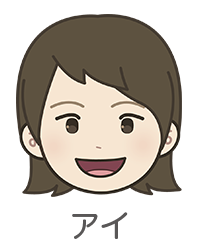

そのとおり。保管場所の床も同じように判断されるでしょうね。さて、次の基準を見てみようか。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントのこう勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
いわゆる「積み上げ高さ制限」と言われるルール。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントのこう勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
いわゆる「積み上げ高さ制限」と言われるルール。
えぇと、最初に「屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合」って書いてあるから、屋内での保管や容器を使った保管の時は、このルールは適用されないってことね。
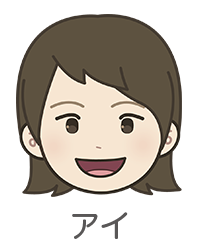

そうだね。いわゆる「野積み」で「バラ積み」の時に適用されるルールだね。
「水平面に対し上方に五十パーセントのこう勾配・・・・」うんぬんって書いてあるけどわかんないわ。
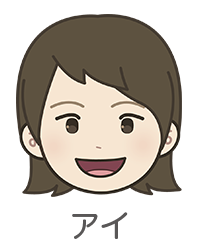

これは図で見ると一目瞭然。図1の向かって左側がこの状態だね。
50%勾配と言うのは、横2に対して高さ1の角度のことなんだ。勾配はこれ以下にしなさいってことだね。
だから、いくら保管場所からはみ出ていないとしても図2のように一部でもこんもりと盛り上がって50%勾配を超えていると違反と言うことになるね。
50%勾配と言うのは、横2に対して高さ1の角度のことなんだ。勾配はこれ以下にしなさいってことだね。
だから、いくら保管場所からはみ出ていないとしても図2のように一部でもこんもりと盛り上がって50%勾配を超えていると違反と言うことになるね。
どうしてこんなルールが出来たの?
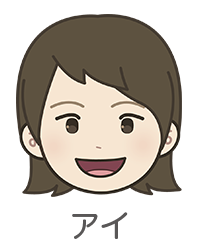

以前は、この勾配のルールは無くて、単に「保管場所から出てはいけない」というだけのルールだったんだけど、「じゃ、はみ出さなければいいんだろ」と言って、てんこ盛りする輩が出てきたんだね。これが全国、あちこちにあって世間からは「産廃富士」なんて揶揄されたんだ。そこで、いくらはみ出さないと言ってもてんこ盛りはダメってことで「2対1勾配」ルールが出来たんだよ。


出典 長岡文明・廃棄物処理法研究会「ここまでわかる!廃棄物処理法問題集」産業環境管理協会, 2010
「2対1勾配」ね。この言い方の方が覚えやすいわね。次は?
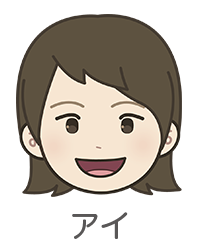

この「2対1勾配」の応用になるんだけど、「囲い」の「塀」「壁」を頑丈に作っているときのルールがある。それが、(2)。
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントのこう勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
これも図で見た方がはるかにわかるよね。これが図1の右側なんだ。
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントのこう勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
これも図で見た方がはるかにわかるよね。これが図1の右側なんだ。
えぇぇと、まず頑丈な壁、「構造耐力上安全な囲い」に寄せ掛けて保管する時は「壁の上端から50センチは下にしろ」ってことね。
次に、そこから2mは水平、つまり、すぐに勾配をつけちゃダメってことね。そして、2m離れたところからは(1)で学習した「2対1勾配」で積み上げていいよってことですね。
次に、そこから2mは水平、つまり、すぐに勾配をつけちゃダメってことね。そして、2m離れたところからは(1)で学習した「2対1勾配」で積み上げていいよってことですね。
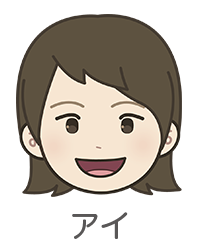

そのとおり。図で描くと判るけど文章で書くと、こんなに長くなっちゃうんだね。
今回は排出事業者の排出事業所における保管のソフト面、特に地下浸透防止と積み上げ勾配について勉強してみました。ご愛読いただきありがとうございます。女子サッカーチーム、アイナック神戸レオネッサの応援もよろしくね。
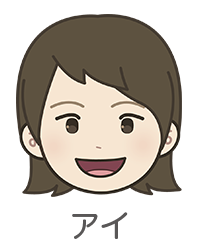
<参考記事>

出典:2021年7月19日 循環経済新聞
(2025年10月)



